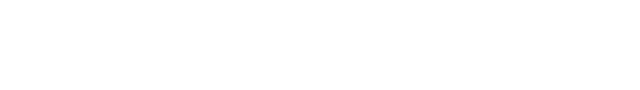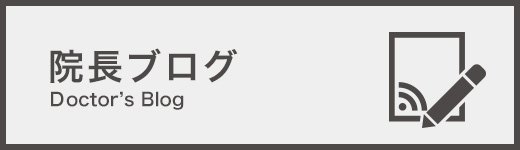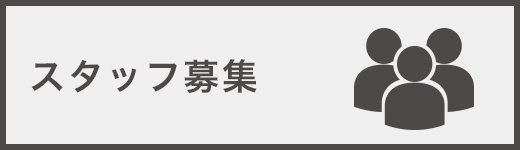スマホ症候群
WHOも認めたスマートフォン症候群(スマホ症候群)
スマートフォン症候群(スマホ症候群)とは、スマートフォンやパソコンの長時間使用によって生じる、首や肩のこり、眼精疲労、ドライアイ、頭痛、不眠、めまい、吐き気などの様々な症状の総称です。
スマートフォンの長時間使用による姿勢の悪さ(特に下を向いた姿勢)や、画面を長時間見続けることによる目の酷使が主な原因です。
世界保健機関(WHO)は新たな「国際疾病分類」(ICD-11)の現代病のリストに「ゲーム障害」を追加しました。
ICD-11での位置付けは精神疾患ですが、スマートフォン(以下スマホ)やタブレット、携帯ゲーム機など携帯端末の使い過ぎによる心身の不調は現代病となってきています。
スマホ症候群は全身を蝕む可能性があります。
スマホ首(ストレートネック)
正式な病名ではありませんが、ストレートネックの原因の一つとして考えられています。
スマホ頭痛
スマホの使いすぎによる頭痛は、主に首や肩の筋肉の緊張、姿勢の悪化、そしてブルーライトの影響などが原因で起こります。
これを「スマホ頭痛」と呼ぶこともあります。長時間のスマホ使用は、緊張型頭痛や片頭痛を引き起こす可能性があります。
特にストレートネックによる緊張型頭痛はパソコンやスマホの使用頻度の上昇に伴い、増加しております。
頭痛外来の詳細はこちら
テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」にスタジオ生出演し、夏の頭痛について解説しました
スマホ認知症
「スマホ認知症」とは、スマートフォンを長時間使用することで、記憶力や集中力の低下、注意散漫などの症状が現れる状態を指す言葉です。医学的な病名ではありませんが、スマートフォンの普及に伴い、近年注目されています。
スマホ内斜視
スマホの使いすぎで起こる、急性内斜視のことです。
これは、スマートフォンやゲームを長時間使用することで、目の筋肉が疲労し、片方の目が内側に寄ってしまう状態を指します。
特に、10代から30代の若い世代で増加傾向にあります。
眼精疲労、ドライアイ
スマホの使いすぎは、眼精疲労とドライアイの主な原因の一つです。画面を長時間見続けることで、まばたきの回数が減少し、目が乾燥しやすくなるため、症状が悪化する可能性があります。
スマホ不眠症
スマホの使いすぎは不眠症の原因になる可能性があります。
スマホから発せられるブルーライトがメラトニンの分泌を抑制し、体内時計を狂わせ、寝つきを悪くしたり、睡眠の質を低下させることが知られています。
また、スマホの刺激によって交感神経が活発になり、リラックスして眠りにつくことが難しくなることもあります。
スマホ症候群の対策
現代社会において、スマホはなくては欠かさないツールとなっていますので、日常生活において全くスマホを使わないで排除するというのは非現実的です。
前頭葉が発達途上である幼児から小学生、中学生くらいまでのお子さんはスマホの使用を抑制することができないことがあるために、特に要注意です。
また、高齢者でもスマホに依存するあまり、スマホ認知症や眼精疲労、ドライアイを引き起こすことがあります。
このように、現代社会ではどの世代でもスマホ症候群を引き起こす可能性があります。
スマホ症候群の対策
・スマートフォンやパソコンの使用時間を制限し、意識的に減らすことが重要です。
・正しい姿勢:背筋を伸ばし、画面を目の高さに保つように意識しましょう。
・休憩:1時間作業したら10~15分程度の休憩を取り、目を休ませましょう。
・適度な運動:首や肩のストレッチ、軽い運動で筋肉の緊張をほぐしましょう。
スマホ昇降の症状がひどい場合は、専門医に相談し、適切な治療を受けるようにしましょう。